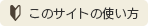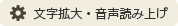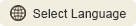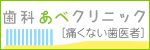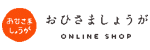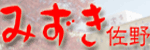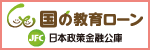前田庠主のことば(平成29年11月23日)
そこでブッダは、まずアリッタに修行僧たちの報告が正しいことを確認して後、アリッタと修行僧たちに、自分の教えの意義を智慧によって究明し、教えをよく理解することを勧めました。また努力にしても理解できないときには、ブッダ自身に問い返し、あるいは賢明な修行僧に質問するように求めました。さらにその教えは正しく理解されたならば、長く利益と安楽をもたらすであろうけれども、それに執着しないように「筏の喩え」を説きました。
それによりますと、ブッダは教えを筏に喩え、教えは、大河の危険で恐ろしいこちらの岸から安穏な向こうの岸へ渡るための筏の如きものにすぎない、と明確に述べているのです。その筏によって向こうの岸に渡ったならば、その筏がどんなに役に立ったにしても、この筏を担いで行くのではなく、陸地に置き捨て、あるいは水に沈めて、行きたいところに出発するのが、筏に対してなすべきことをなしたことになるのです。「筏は渡るためにあるのであって、取っておくためにあるのではない。あなたたちはもろもろの教えといえども必要な条件がなくなれば捨て去るべきである。」(『原始仏教』IV、春秋社、2004、331-2)この比喩で筏に喩えられているのは言うまでもなくブッダの教え、一般的には宗教の教え、通例絶対的と見做されている宗教の教義です。宗教の教義というものは、その時の歴史的・社会的・個人的あるいは集団の諸条件の中で説かれるものであり、絶対的なものではなく、その条件が変われば捨て去るべきものなのです。このように自由で寛容な精神こそ、文明の発達で、かつて人類が経験したことのないグローバル化に直面し、多宗教、多文化の他民族が共に生きていかざるを得ない今日の世界で、人類が平和に共生するためには是非とも必要な条件ではないでしょうか。
平成29年11月23日
史跡足利学校庠主 前田專學