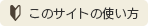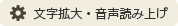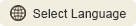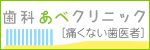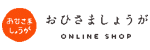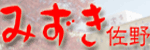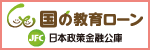トップ
> 意匠登録見本 雲井織等
意匠登録見本 雲井織等

4種13点(附商標)
明治中期に足利でつくられた織物見本です。
これら4種13点は、明治21年(1888)に日本で初めて定められた意匠条例に基づいて、明治22年(1889)に意匠登録第1号となった雲井織から和合絣(かすり)、綾千鳥、錦線織、花錦織、新玉織、黄金織、花鳥織と続き第63号の錦名白飛織に至る9件の意匠登録当時の原品です。
これら原品は国のいずれの機関にも保管されておらず、現存する唯一の歴史資料として貴重です。
これら9件の織布(しょくふ)は、綿平織、綿綾織、絹綿平織、絹平織など織り方に創意工夫を凝らして新しい意匠を案出したもので、新製品に期待をかける足利の人々の熱意が結集したものといえます。
とりわけ足利市家富町の機屋・須永由兵衛が考え出した雲井織は、意匠登録第1号の製品として、近代史上、近代日本における知的財産権の確立期の記念すべき位置を占めています。
もとより工業技術史上、足利織物の先進性を裏づける点でも意義深いものとなっています。
雲井織は、「綿縮み」と呼ばれる綿平織で、織物の全面に細かい「しぼ」を持ち、さらっとした手触りで吸湿性のある布地に仕上げられています。
この「綿縮み」は、横糸に右ひねり2本と左ひねり2本の強撚糸を交互に織り込こんでつくり出したものです。
雲井織の意匠は、色付きのたて糸を等間隔に配列した縞柄で、茶色と青色の二種のたて糸が布地に浮き出し、その糸のところどころに小星紋(小さい玉状のループ紋様)が織り出される点に特徴があります。
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先