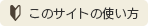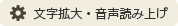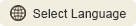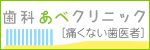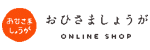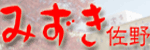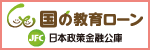トップ
> 銅造 菩薩立像(どうぞう ぼさつりゅうぞう)
銅造 菩薩立像(どうぞう ぼさつりゅうぞう)

像高 5.25cm
鎌倉時代末~室町時代頃
金銅製で一鋳(いっちゅう)の無垢像です。頭部に垂髻(すいけい)を結い、両腕とも肘を曲げ、右腕前で宝剣を構え、右手の掌を上に向け、宝珠と推定されるものを持っています。
条帛(じょうはく)は左肩から腹前を横切り、折り返しの裳をつけ、背面の表現は頭部を除き、扁平にあらわし、すべて省略しています。
台座は蓮弁(れんべん)に間弁をつけ、反花(かえりばな)を表現しています。
伝来によれば、本像は市内樺崎町、樺崎八幡宮の奥、入谷(いりやつ)の長家(ちょうけ)に伝来した小金銅仏です。
同じく長家に伝来する系図によれば、長氏は戦国時代に樺崎の谷に居住した土豪で、三浦義明の五男、長井五郎義季の末裔とされ、15世紀末~16世紀初の鑁阿寺文書(ばんなじもんじょ)に長次郎の名が確認できます。
この像は右胸前で構え、左手に宝珠と思われるものを持つことから虚空蔵菩薩立像と推定され、製作年代は鎌倉時代末期から室町時代頃と推定されます。
樺崎町の長家に長く伝来したという歴史的な由緒も明らかで、中世の作風を伝える小金銅仏として貴重なものです。
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先