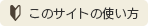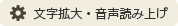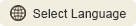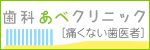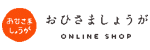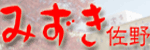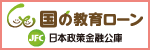トップ
> 長林寺の鰐口(ちょうりんじのわにぐち)
長林寺の鰐口(ちょうりんじのわにぐち)

縦 18.0cm、横 16.0cm
銅製
室町時代
鰐口とは、寺社の堂前や仏殿の軒につるし、参拝者がお参りをするとき引綱を引いて打ち鳴らす金属製の鈴のことで、永禄(えいろく)11年(1568)、尾州の僧が山川長林寺(ちょうりんじ)の前身である常州東林寺に寄進したものです。
この鰐口は隆起圏線を三条にめぐらし、内・外区と銘帯(めいたい)をわけています。
天正年間に現在の足利市山川町へ移転の際に、他の資料とともに長林寺に持ってきた物と思われ、移転された事が銘帯に記されており、歴史的背景が良く解ります。
保存状態は良く、室町時代(戦国期)の作として希少です。
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先