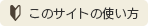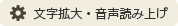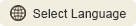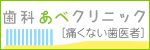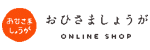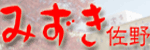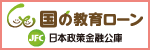トップ
> 石造層塔(伝足利義兼供養塔)
石造層塔(伝足利義兼供養塔)

寸法: 現存 101.0cm
材質: 凝灰岩製
樺崎寺跡の足利氏御廟跡と推定される建物跡付近に、初重(しょじゅう)軸部に笠(かさ)・軸の石を2つ重ねて建っていた石造層塔です。
初重軸部の四面には金剛界四仏の種子が大きく彫られています。
その後、足利氏御廟跡基壇を発掘調査した際に、残りの笠の一部と、一番上にのる九輪が出土しました。
現在は史跡の復元整備に伴い、すべて足利市が保管しています。
市内大岩町にある「大岩山石造層塔」は建長8年(1256)の銘が彫られた、市内に現存する最古の石造物として栃木県指定文化財となっており、樺崎寺跡の本石造層塔と比較すると以下の点で違いが見られます。
- 初重軸部の陰刻が大岩山は肉彫の仏像であるのに対し、樺崎寺跡のものは種子であること
- 笠部の軒反(のきぞり)が大岩山はほとんど見られないのに対し、樺崎寺跡のものはやや両端が反ること
以上の違いから樺崎寺跡のものは大岩山のものよりやや新しい形態のものであることから、13世紀後半の時期が推定されます。
※現在、保存管理のため足利市教育委員会で保管しています。
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先