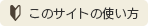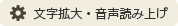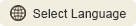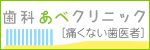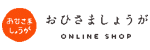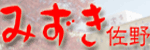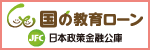トップ
> 放生会の碑(ほうじょうえのひ)
放生会の碑(ほうじょうえのひ)

総高 105.9cm
安山岩製
江戸時代
放生会(ほうじょうえ)とは、仏教の不殺生、不食肉の戒めに基づき、鳥や魚などを野や海などに放って命を救う法会(ほうえ)のことを言います。
この碑は寛延(かんえん)2年(1749)に、足利本町の丸山相学が講中を代表して建てたもので、碑文は1行が25字~27字で10行あり、総数256字の漢文体で以下のような内容が書かれています。
『中世に(八幡宮で)行われていた放生会を、(廃れてしまっていたので)募金によって延享(えんきょう)2年(1745)年に復活することができたので、末永く継続することを願う』
本碑は、八幡神信仰と放生会との関係、源氏ゆかりの下野國一社八幡宮における放生会の実態を知る上でも、「延文記録」(えんぶんきろく)と共に、貴重な資料です。
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先