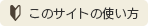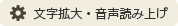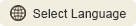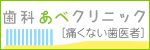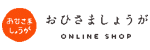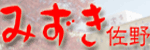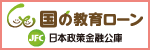トップ
> 回漕問屋忠兵衛の石燈籠(かいそうどんやちゅうべえのいしとうろう)
回漕問屋忠兵衛の石燈籠(かいそうどんやちゅうべえのいしとうろう)

総高 375.0cm
安山岩製
江戸時代
寛永(かんえん)元年(1645)以降、明治21年(1888)の両毛鉄道開通まで、両毛地方の輸送の主力は舟運でした。
本石燈籠は、「北猿田河岸」(きたやえんだがし)の中で最も古い歴史をもつ回漕問屋であった「問忠」が御神燈として、「船中安全」を祈願して嘉永(かえい)2年(1849)9月に建てた、高さ3mを超える大型なものです。
明治20年(1887)に「問忠」廃業後、両毛鉄道足利駅の近くにあった伊勢神社に移設されました。
その後、大正2年(1913)に伊勢神社が現在地に移転するに伴い現位置に移設されました。
なお、平成23年の東日本大震災に伴い、火袋が破損し、修理を施しています。
江戸時代において、足利・桐生の舟運の外港であった「北猿田河岸」の繁栄のようすを具体的に示す考古史料として貴重です。
掲載日 令和5年2月1日
このページについてのお問い合わせ先