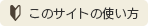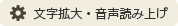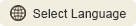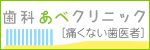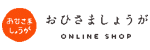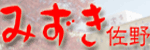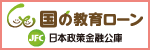トップ
> 彦谷神楽(ひこやかぐら)
彦谷神楽(ひこやかぐら)

彦谷神楽は、明治28(1895)年に当地の松島竜三郎氏ほか20数人によって、創始されたと伝わっています。
同神楽は隣の地区にある大前町大原神社の御神楽(大和流渋井派)から派生して、独自に発展を遂げて今に至っており、テンポが他の神楽団体に比べて、早目であることや一切口上がないところが特徴的です。
年間の活動実態は地元中心の活動で、春と秋の例大祭は地元の神社で奉納神楽を催しています。座数は13座あり、もっぱら6~7座を演舞しています。
保存会は、葉鹿町彦谷の相続人のみに伝承する習慣で、明治28年の創始以来の座数を減らすことなく、100年以上継承しています。現在は後継者育成とともに技の継承と研鑽に努めています。
彦谷神楽は、ほかの市指定の無形文化財になっている神楽と比べても何ら遜色のないものであり、地元の氏子組織の強い支援のもと継承してきた民俗芸能として貴重です。
| 日付 | 奉納場所 |
|---|---|
| 4月第3日曜日(春季例大祭) | 篠生神社(葉鹿町) |
| 5月3日(春季例大祭) | 湯殿山神社(葉鹿町) |
| 葉鹿町夏祭 | |
| 10月第3日曜日(秋季例大祭) | 篠生神社(葉鹿町) |
| 10月第4日曜日(秋季例大祭) | 日枝神社(葉鹿町) |
※奉納予定は変更になる可能性があります。
文化課職員の取材ノート
広報あしかがみ(2021年12月号)の紹介記事に書ききれなかったことを箇条書きで掲載します。
- 彦谷神楽保存会の活動
- 会員10人…50代から80代まで
- 葉鹿町の人が中心で活動しているが、町外の人も歓迎
- 若い人や小学生も見学に来る
「勉強や部活、仕事の合間の息抜きとして、気軽に顔出すだけでもいい。遊びに来てくれたら嬉しい。」by会長 - 1960年代頃まで、同町内には「みどり劇団」という演劇団体があり、その劇団員を神楽師にスカウトしたこともあった。
- 神楽の練習
- 練習期間 … 奉納する2か月前から、週1回集まれる日(火曜日になることが多い)
- 練習場所 … 彦谷自治会館のホール
- 互いに自分の十八番とする演目を教え合う。
- 演目
- ひとつのお祭りにあたり5~7曲くらいを披露する。
天児屋根命(あまのこやねのみこと)の舞、猿田彦命(さるたひこのみこと)の舞、天之岩戸開(あまのいわとびらき)の舞、事代主命(ことしろぬしのみこと)(恵比寿)の舞、八幡大神命(やわたのおおかみのみこと)の舞、住吉大神(すみよしのおおかみ)の舞、大山祇命(おおやまずみのみこと)の舞


天之岩戸開の舞(日枝神社にて)



神楽の道具類
彦谷神楽の動画
彦谷自治会館の地図
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和5年7月19日
このページについてのお問い合わせ先