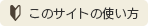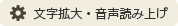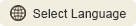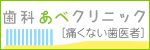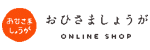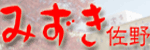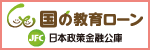医療費助成制度Q&A
医療費助成制度に関しての、よくある質問と回答です。
Q1.母子健康手帳が交付される前に切迫流産で入院をしたのですが、その入院費は妊産婦医療費助成の対象になりますか?
妊娠届出をした月の初日から出産(流・死産)した月の翌月末日までが対象となりますが、その前にも明らかに妊娠に起因する疾病により治療を受けた場合は、その治療費についても助成を受けることができます。専用の申請書を用いて医療機関で保険診療点数の証明を受ける必要があります。なお、検査・不妊治療は助成対象外です。(不妊治療はこども相談課等で別途助成があります。)
Q2.重度心身障がい者医療費助成制度はどのような方が対象になりますか?
重度心身障がい者医療費助成は、令和4年4月1日より「精神障がい者保健福祉手帳1級」の方も対象となりました。なお、以下に該当する方が対象となります。
- 身体障がい者手帳の1、2級の方
- 療育手帳A1、A2の方
- 身体障がい者手帳3、4級で知能指数が50以下の重複障がいの方
- 知能指数35以下の方
- 精神障がい者保健福祉手帳1級の方
Q3.ひとり親家庭医療費助成の手続きをしたのですが、受給資格者証はいつ送付されますか?
登録申請手続きは児童扶養手当や遺族年金の請求中であっても行うことができます。なお、受給者証の交付は児童扶養手当認定後または遺族年金証書発行後になります。 領収書は大切に保管しておいてください。(認定には、所得制限があります。)
児童扶養手当受給者の方
児童扶養手当の認定を受けられた後、受給資格者証を郵送しています。(認定後2ヶ月程かかります。)
遺族年金受給者の方
遺族年金証書の写し(対象者全員分)を提出いただいた後、資格の審査を行い、該当となった方には受給資格者証を郵送しています。(資格の審査は2ヶ月程かかります。)
なお、非該当となった方にも結果をお知らせする通知を郵送しております。
Q4.ジェネリック医薬品がある薬で先発医薬品を希望したら追加料金が発生しました。医療費助成で還付されますか。
令和6年10月よりジェネリック医薬品がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は医療費にプラスして「特別の料金」を支払う必要があります。こちらの「特別の料金」に関しては、医療費助成の助成対象外となります。
Q5.領収書を郵送で申請することはできますか。
医療費助成を郵送で申請することは可能です。ご自身で切手と封筒を用意いただき、下記まで送付してください。なお、領収書は原本に限り申請できますが、回収になるためお返しはできません。領収書原本が必要な場合には、領収書の原本とコピーを持参し、足利市役所こども家庭政策課もしくは公民館(織姫・助戸を除く)に申請してください。
郵送先:〒326-8601足利市本城三丁目2145番地足利市役所こども家庭政策課子育て支援担当
※料金受取人払封筒の配布は令和6年12月27日をもって終了しました。
Q6.入院をしたのですが助成金の振込額が支払った金額より少ないのですが?
医療費助成では健康保険が適用となる診療等について助成を行っていますので、差額ベッド代・食事代などの保険外の支払いについては対象となりません。この場合、助成を受けられるのは一部負担金になります。
また、助成金は健康保険から支給される高額療養費や付加給付金等を差し引いて支給しています。高額療養費や付加給付金等についてはご加入の健康保険にお問い合わせください。
| 医療費総額(10割) | |
| 保険給付額 | 一部負担金 |
上記の『一部負担金』が医療費助成の対象
助成額 = 一部負担金 - ( 高額療養費 ・ 付加給付金など )
限度額適用認定証の活用について
入院予定や入院中の方については、医療機関に支払う前に健康保険から、『限度額適用認定証』の交付を受け保険証と一緒に提示することにより、医療機関からの請求について高額療養費を受けた自己負担限度額での支払いで済みますので、高額療養費に該当する医療費を支払いの場合、積極的に『限度額適用認定証』を利用くださいますようお願いいたします。『限度額適用認定証』をお持ちの方は、申請の際、『限度額適用認定証』のコピーを領収書と一緒に添付してください。
高額療養費の手続きについて
高額な医療費を支払いの場合で、高額療養費の自己負担限度額が不明の場合は、医療費助成の申請は後日となることもあります。その場合は、先に健康保険からの高額療養費を申請後、『高額療養費支給決定通知書』等を添付のうえ領収書と一緒に医療費助成を申請していただくことになります。
-
栃木県国民健康保険の方
栃木県国民健康保険から手続きのご案内を差し上げます。 -
栃木県国民健康保険以外の方
自動的に振り込まれる場合と手続きが必要な場合があります。ご加入の健康保険に確認ください。 -
後期高齢者医療制度の方
栃木県後期高齢者医療広域連合から手続きのご案内を差し上げます。
初回申請方式をとっていますので、一度手続きされた方は自動振込になります。
高額療養費(限度額適用認定証)や付加給付については、加入している健康保険組合や共済組合にお問い合わせください。
自己負担限度額(平成29年8月1日から)
| 区分 | 自己負担限度額 | 多数該当(*1) |
|---|---|---|
| ア | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
| ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| エ | 57,600円 | 44,400円 |
| オ | 35,400円 | 24,600円 |
| 自己負担限度額 | |||
|---|---|---|---|
| 外来 (個人単位) |
入院と世帯合算 | ||
| 現役並み所得者 3 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 多数回※は140,100円 |
||
| 2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 多数回※は93,000円 |
||
| 1 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 多数回※は44,400円 |
||
| 一般の方 | 18,000円(年間上限は144,000円) |
57,600円 多数回※は44,400円 |
|
| 低所得者 |
2 |
8,000円 | 24,600円 |
|
1 |
15,000円 | ||
※ 多数該当とは=過去12ヶ月間に4回以上該当した場合、4回目以降。