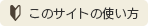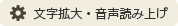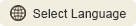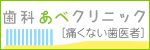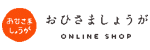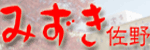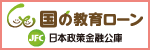利用者負担額(保育料)について
幼児教育・保育の無償化について(令和元年10月1日~)
令和元年10月1日より、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳児クラスのすべての子どもたちの利用料を無償化します。※教育認定は満3歳、保育認定は3歳児クラスのお子さまから無償化が適用されます。
併せて、市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもたちの利用料も無償化します。
第2子以降利用者負担額(保育料)の無償化について(令和6年4月1日~)
栃木県より令和6年10月から県内の自治体と共同で第2子の保育料無償化を実施すると発表がありました。本市では県との共同事業に先駆けて、令和6年4月から市独自で 「第2子利用者負担額(保育料)の無償化」を実施します。
※第3子以降のお子様は、令和6年3月以前から無償化対象です。
対象者
- 以下のすべてに当てはまる方が対象です。
- 足利市に住民登録がある方
- 認可保育施設の0~2歳児クラス(年少クラス未満)に在籍する方
- 保護者が現に養育しているお子さまのうち、第2子にあたる方
※第1子として数えるお子さまは原則18歳以下ですが、学生等で保護者が扶養している 場合は18歳を超えても第1子とみなしています。就労等により扶養を外れている場合は該当しません。
※3歳児クラス以上の保育料については、上記の幼児教育・保育の無償化によりすべてのお子さまが令和元年度から無償化対象です。3歳児クラス以上から実費負担となっている副食費は、第2子無償化の適用はありませんのでご注意ください。
申請方法
- 必ず申請書の提出が必要です。 在籍する施設を通して「第2子以降利用者負担額減免申請書」をご提出ください。
足利市利用者負担額表
| 保育 認定 |
利用者負担 (月額) | ||
| 階層 区分 |
3号認定/2号認定 (3歳未満児) |
||
| 保育標準時間 | 保育短時間 | ||
| 1 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 |
8,500 〔4,200〕 |
8,500 〔4,200〕 |
|
| 特例 |
3,700 〔 0〕 |
3,700 〔 0〕 |
|
| 4 |
13,000 〔6,500〕 |
12,800 〔6,400〕 |
|
| 特例 |
6,000 〔 0〕 |
5,900 〔 0〕 |
|
| 5 |
17,300 〔8,600〕 |
17,000 〔8,500〕 |
|
| 特例 |
8,600 〔 0〕 |
8,500 〔 0〕 |
|
| 6 |
22,000 〔11,000〕 |
21,700 〔10,800〕 |
|
| 7 |
28,000 〔14,000〕 |
27,600 〔13,800〕 |
|
| 8 |
36,500 〔18,200〕 |
35,800 〔17,900〕 |
|
| 9 |
42,500 〔21,200〕 |
41,800 〔20,900〕 |
|
| 10 |
45,900 〔22,900〕 |
45,200 〔22,600〕 |
|
| 11 |
49,300 〔24,600〕 |
48,500 〔24,200〕 |
|
階層区分の定義
保育認定
- 生活保護法による被保護世帯(単給世帯も含む)
以下の階層は第1階層を除く市民税所得割額の額の区分が次の区分に該当する世帯が対象になります。
- 市民税非課税世帯
- 市民税均等割課税世帯
- 48,600円未満
- 48,600円以上77,200円未満
- 77,200円以上105,500円未満
- 105,500円以上147,600円未満
- 147,600円以上189,600円未満
- 189,600円以上252,900円未満
- 252,900円以上301,000円未満
- 301,000円以上
各階層の特例はその階層のうち、母子(父子)世帯並びに在宅障がい児(者)のいる世帯等を指します。
市民税所得割額確認方法
【市民税・県民税・森林環境税税額決定・納税通知書】をお持ちの方…課税明細書の「税額控除前所得割額」から「調整控除額」を差し引いた額が算定基礎です。
【給与所得に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書】をお持ちの方…「税額控除前所得割額④」から調整控除額を控除した額が保育料算定基礎になります。
※住宅借入金等特別控除や寄付金控除については、算定基礎から差し引きません。
注意事項
- クラス年齢(○歳児)については、年度当初(4月2日時点)のお子さまの満年齢により決定します。
- 階層区分は、4月~8月は前年度分の市町村民税、9月~翌年3月は当年度分の市町村民税により決定しお知らせする予定です。
- 市民税所得割課税額を計算する際、調整控除以外の税額控除(配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除等)は適用されません。
- 利用者負担額は、児童の父母の課税額の合計により算定するほか、同居の祖父母など父母以外の扶養義務者の課税額を合計する場合があります。
- 令和6年4月以降、第2子以降の児童の利用者負担額は無償化(0円)となります。施設を通して、第2子以降保育料減免事業の減免申請書の提出が必要です。保護者が現に養育している一番上の年齢のお子さまから数えて2番目以降にあたるお子さまの利用者負担額が無償化の対象です。就労等により扶養から外れているお子さまは第1子として数えません。
- 第2階層から第5階の世帯で、母子(父子)世帯並びに在宅障がい児(者)のいる世帯等の場合は、特例に該当し半額相当の利用者負担が適用されます。ただし、家計の主宰者が同居の祖父母などの場合は特例の適用外となる場合があります。
- 利用者負担額の算定に必要な課税書類の提出がない、市町村村民税の申告がないなど、課税額の確認ができない場合は、各認定区分の最高階層の利用者負担額が適用されます。なお、決定後に確定申告がされた場合でも当初に遡って利用者負担額を変更することはありません。
- この利用者負担額は、子ども・子育て支援新制度の対象となる教育・保育施設、地域型保育事業を利用する場合に適用されます。そのため、新制度未移行幼稚園(私学助成幼稚園)等を利用する際は、各施設で設定した保育料をご負担いただくこととなりますが、月額25,700円分までは教育・保育無償化により無償(0円)となります。
- この利用者負担額のほか、各施設においてバス代や教材費、行事費などの実費の負担が必要な場合があります。実費の部分は無償化の対象とはなりませんのでご注意ください。
- 推定年収は、父・母(税法上の扶養の範囲)・子ども2人をモデル世帯としておおまかな目安として表記しています。必ずしも対応する階層区分に該当するとは限りません。
修正申告や更正などにより、市民税が変更になった場合は保育課までご連絡ください。
変更となった市民税の額により、利用者負担額(保育料)が変更になることがあります。