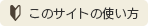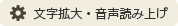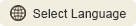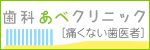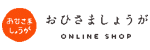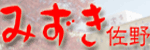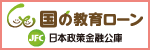幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育無償化
令和元年10月1日より、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳児クラスのすべての子どもたちの利用料を無償化します。※教育認定は満3歳、保育認定は3歳児クラスのお子さまから無償化が適用されます。
併せて、市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子どもたちの利用料も無償化します。
また、幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用する子どもの施設等利用費の給付方法が、令和5年度より償還払いから現物給付へと変更になりました。詳しくは以下をご覧ください。
 幼児教育・保育無償化(概要版)(pdf 201 KB)
幼児教育・保育無償化(概要版)(pdf 201 KB) 幼児教育・保育無償化(私学幼稚園)(pdf 472 KB)
幼児教育・保育無償化(私学幼稚園)(pdf 472 KB) 幼児教育・保育無償化(幼稚園・こども園(教育認定))(pdf 485 KB)
幼児教育・保育無償化(幼稚園・こども園(教育認定))(pdf 485 KB) 幼児教育・保育無償化(保育所・こども園 保育認定) (pdf 371 KB)
幼児教育・保育無償化(保育所・こども園 保育認定) (pdf 371 KB) 幼児教育・保育無償化(認可外保育施設) (pdf 318 KB)
幼児教育・保育無償化(認可外保育施設) (pdf 318 KB) 幼児教育・保育無償化(企業主導型保育) (pdf 323 KB)
幼児教育・保育無償化(企業主導型保育) (pdf 323 KB)
保育所(園)、認定こども園(保育部分)を利用する方
対象者・利用料(保育料)
- 保育所(園)、認定こども園(保育部分)を利用する足利市の認定を受けた3歳児(年少)クラスから5歳児(年長)クラスの子ども
- 保育所(園)、認定こども園(保育部分)を利用する足利市の認定を受けた0歳児クラスから2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子ども
- 保育所(園)・認定こども園(保育部分)については、教育・保育給付認定の手続きを行う必要があります。
- 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもや世帯の第3子以降の子どもについては、副食(おかず代)の費用が免除されます。
私学幼稚園、新制度幼稚園、認定こども園(教育部分)を利用する方
対象者・利用料(保育料)
- 幼稚園、認定こども園(教育部分)を利用する足利市の認定を受けた満3歳から5歳児クラスまでのすべての子ども
- 新制度幼稚園及び認定こども園(教育部分)については、教育・保育給付認定の手続きを行う必要があります。
- 私学幼稚園については、施設等利用給付認定の手続きを行う必要があります。
- 私学幼稚園の利用料(預かり保育料部分を除く)の無償化については、月額上限2.57万円です。
- 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもや世帯の第3子以降の子どもについては、副食(おかず代)の費用が免除されます。
私学幼稚園、新制度幼稚園、認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用する方
対象者・利用料
- 「保育の必要性の認定」を受けた3歳児(年少)クラスから5歳児(年長)クラスの子ども
- 「保育の必要性の認定」を受けた住民税非課税世帯の満3歳児クラスの子ども
- 「保育の必要性の認定」として、施設等利用給付認定の手続きを行う必要があります。
- 「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)となります。
- 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じた月の支給限度額(450円×利用日数)の範囲で預かり保育の利用料が無償化されます(支給限度額月1.13万円)。
(注1)保育の必要性の認定として認めた要件以外で預かり保育を利用した場合は無償化の対象となりません。
(注2)給食代、おやつ代が利用料に含まれる場合、支給される給付額は給食代、おやつ代を差し引いた額となります。
(注3)無償化の上限額の範囲内であれば、利用者から利用料を徴収することはありませんが、上限額を超える場合は、超えた分の利用料について、施設にお支払いください。
認可外保育施設・一時預かり事業等を利用する方
対象者・利用料
- 足利市の「保育の必要性の認定」を受けた3歳児(年少)クラスから5歳児(年長)クラスの子ども
- 足利市の「保育の必要性の認定」を受けた住民税非課税世帯の0歳児クラス~2歳児クラスの子ども
- 「保育の必要性の認定」として、施設等利用給付認定の手続きを行う必要があります。
- 3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもは、月額3.7万円までの利用料が無償化されます。
- 0歳児クラスから2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の子どもは、月額4.2万円までの利用料が無償化されます。
(注1)保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
(注2)「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)が必要です。
(注3)一度施設等へ利用料をお支払いし、後で償還払いにより給付を受け取る方法となります。なお、給付に必要な申請書類については施設を通してご案内いたします。
対象となる施設・事業
- 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
(注1)認可外保育施設とは、乳幼児を保育することを目的とする施設で、都道府県知事等の認可(児童福祉法第35条第4項の認可)を受けていない施設のことです。
(注2)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。
企業主導型保育事業を利用する方
- 保育の必要性のある3歳児(年少)クラスから5歳児(年長)クラスの子ども
- 保育の必要性のある0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯の子ども
- 無償化の対象となるためには、利用している企業主導型保育施設に対し、必要書類の提出を行う必要があります(地域枠利用者に限る)。
保育の必要性の認定について
保育の必要性の認定を受ける場合、下記のいずれかに該当することが必要です。
- 就労
- 1ヶ月あたり64時間以上の就労を常態とする場合
- フルタイムパートのほか、パートタイム、夜間など基本的にすべての就労に対応
- 居宅内の労働(自営業、在宅勤務等)を含みます。
- ただし、給与の支払いを伴わない就労は認定できません。
- 1ヶ月の就労時間状況により、保育標準時間と保育短時間に振り分けられます。
- 妊娠、出産
- 妊娠・出産により家庭保育が困難な場合
- 里帰り出産等、出産による認定期間は、産前産後あわせて4ヶ月となります。
- 保護者の疾病・障がい
- 保護者が疾病・障がいにより、家庭保育が困難な場合
- 介護・看護
- 同居または長期入院等している親族の介護・看護により家庭保育が困難な場合
※就労要件と同等の介護・看護時間が必要となります。
- 同居または長期入院等している親族の介護・看護により家庭保育が困難な場合
- 災害復旧
- 求職活動 (起業準備を含みます)
- 求職期間は3ヶ月となります。保育認定を受けられる期間も3ヶ月です。延長はありません。
- 妊娠中の求職活動による認定は原則として認められません。
- 就学
- 職業訓練校等における職業訓練を含みます。
- 虐待やDVのおそれがあること
- その他、上記に類する状態として認める場合
保育を必要とする事由の変更が生じたら?
- 求職活動をしていたが、就労先が見つかった。
- 子どもが生まれ、育児休業を取得する。
- 育児休業を取得していたが、満了となったので職場に復帰したい。
- 会社を辞めてしまった。
- 仕事の時間が変わった。
- 離婚/結婚した。
以上のような理由で保育を必要とする事由の変更が生じたら、すみやかに通っている施設もしくは保育課まで連絡及び申請をしてください。
無償化等の認定申請に関する書類について
無償化に関する教育・保育給付認定や施設等利用給付認定の申請書類については、こちら(認可保育施設等申請に関する様式一覧)をご覧ください。
掲載日 令和5年2月1日
更新日 令和6年7月18日
このページについてのお問い合わせ先