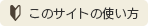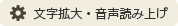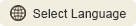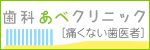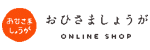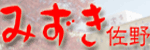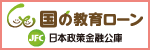選挙のいろいろ
選挙の意義
「選挙」は、私たち一人ひとりのために。
私たちは、家族や地域、学校や職場など、さまざまな場でくらしています。私たちの生活や社会をよくするためには、私たちの意見を反映させてくれる、代表者が必要であり、その代表者を決めるのが「選挙」なのです。
みんなの代表
選挙によって選ばれた代表者は、国民や住民の代表者となります。したがって、その代表者が職務を行うに当たっては、一部の代表としてではなく、すべての国民や住民のために政治を行うことになります。
多数決
民主政治の原則である多数決は、人々の意見を集約し、決定する際に用いる方法です。より多くの支持を得た者を代表者とすることによって、政治の安定化を図ります。
身近な選挙
「選挙」とは、私たちの代表を選び私たちの意見を政治に反映させるためのもの。そのためにも、私たち一人ひとりが「選挙」に関心を寄せることで、「選挙」はもっと身近なものになるといえます。
憲法と選挙
選挙に関する規定を定めた公職選挙法は、日本国憲法第15条で明記されている「公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する」という憲法の精神にのっとっています。
選挙と政治
日本は国民が主権を持つ民主主義国家です。
選挙は、私たち国民が政治に参加し、主権者としてその意思を政治に反映させることのできる最も重要かつ基本的な機会です。
政治と国民
「人民の、人民による、人民のための政治(政府)」。民主主義の基本であるこの言葉は、私たちと政治との関係を象徴する言葉です。
国民が正当に選挙を通して自分たちの代表者を選び、その代表者によって政治が行われます。
選挙の基本原則
選挙制度については、最も基本的な原則(普通選挙・平等選挙・秘密投票・直接選挙)が憲法に定められています。
普通選挙
普通選挙とは、財産の多少や納税額が多いか、少ないか、性別などにより選挙権に差別をもうけない制度をいいます。
平等選挙
平等選挙とは、個々の選挙人の行使する選挙権の内容に制度上の差をもうけることなく、平等にする制度をいいます。
秘密投票
すべての選挙における投票の秘密が守られ、選挙人の自由な意思による選挙権の行使が保障されなければなりません。
直接選挙
一般の選挙人が、直接その選挙の目的である公職につくべき者を選挙するのが直接選挙です。
選挙制度のあゆみ
制限選挙の時代(明治22年(1889年)~大正14年(1925年))
明治22年に衆議院議員選挙法が制定されましたが、そのときは、満25歳以上の男子で、直接国税を15円以上納める人に選挙権が与えられ、被選挙権については、満30歳以上の男子で選挙権と同じ納税要件を満たしている人に限られていました。
初めて行われた明治23年7月1日の衆議院議員総選挙で、有権者は、450,872人で、当時の日本の人口の約1.1%にすぎませんでした。
明治33年の改正で、納税要件は被選挙権については廃止、選挙権については緩和(直接国税15円以上から10円以上)されました。
大正8年の改正では、納税要件が、直接国税3円以上納める人としたので有権者の数も大幅に増加しました。
男子のみ普通選挙の時代(大正14年~昭和20年(1945年))
第一次大戦後、納税要件などの資格制限のない普通選挙を求める運動が展開され、大正14年に普通選挙法が成立しました。選挙権については、納税要件が廃止され、満25歳以上の男子については、だれでも選挙権を有するという普通選挙制度が初めて確立されました。
男女平等普通選挙の時代(昭和20年~平成28年(2016年))
太平洋戦争後の占領下における民主化政策のもとで、昭和20年12月、衆議院議員選挙法が改正され、女子に対しても男子と同じ条件で選挙権、被選挙権が認められ、ここにおいて、わが国の選挙制度史上初めて完全普通選挙制度が確立されました。
また、選挙権の年齢の要件は、それまでの満25歳から満20歳に、被選挙権についても満30歳から25歳に引き下げられました。
成年者による普通選挙の保障は、その後、制定された日本国憲法において明記され、憲法上の原則とされています。
選挙権年齢の引き下げ(平成28年~現在)
公職選挙法の改正により、平成28年の参議院議員選挙から選挙権年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。
選挙の種類
| 選挙の種類 | 選挙管理機関 | 任期 |
|---|---|---|
| 衆議院議員総選挙(比例代表) |
中央選挙管理会 |
4年 |
| 参議院議員通常選挙(比例代表) |
中央選挙管理会 |
6年 |
| 衆議院議員総選挙(選挙区) |
栃木県選挙管理委員会 |
4年 |
| 参議院議員通常選挙(選挙区) |
栃木県選挙管理委員会 |
6年 |
| 栃木県議会議員選挙 |
栃木県選挙管理委員会 |
4年 |
| 栃木県知事選挙 |
栃木県選挙管理委員会 |
4年 |
| 足利市議会議員選挙 |
足利市選挙管理委員会 |
4年 |
| 足利市長選挙 |
足利市選挙管理委員会 |
4年 |
- 衆議院議員総選挙のときは、最高裁判所裁判官の国民審査があわせて行われます。
選挙権(選ぶ権利)
| 選挙の種類 | 選挙権の要件 |
|---|---|
| 参議院議員・衆議院議員 |
満18歳以上の日本国民 |
| 栃木県知事・栃木県議会議員 |
満18歳以上の日本国民 引き続き3か月以上本市に住所のある人 上記の人が栃木県内の他の市町村に住所を移し、3か月にならない場合も引き続き選挙権があります。 |
| 足利市長・足利市議会議員 |
満18歳以上の日本国民 引き続き3か月以上本市に住所がある人 |
被選挙権(選ばれる権利)
| 選挙の種類 | 被選挙権の要件 |
|---|---|
| 参議院議員・知事 |
満30歳以上の日本国民 |
| 衆議院議員・市町村長 |
満25歳以上の日本国民 |
| 県議会議員・市議会議員 |
満25歳以上の日本国民 引き続き3か月以上市町村の区域内に住所のある人 |
選挙権と被選挙権のない人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く。)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人
- 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
- 政治資金規正法違反の罪を犯し刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人
- 選挙犯罪により刑に処せられ、選挙権、被選挙権が停止されている人
投票
選挙権のある人は、投票日に投票所入場券に書かれた投票所で、投票時間中(午前7時から午後7時まで)に選挙人名簿との対照(本人であることの確認)を済ませてから投票することになっています。
投票用紙には、候補者の氏名(比例代表選出議員選挙では政党名等)を書きます。2つ以上の選挙が同時に行われるときは、投票用紙の色等を区別してありますので、注意して投票しましょう。
例外的な投票方法
- 代理投票
身体の不自由な人で、候補者の氏名等を自書できないときは、投票管理者に申請すれば、補助者が本人に代わって投票用紙にその人の指示する候補者氏名等を記載します。 - 点字投票
目の不自由な人は、投票管理者に申請すれば点字投票できます。
期日前(不在者)投票
次の理由に該当する場合は、投票日前でも期日前(不在者)投票ができます。
- 仕事に従事中の場合
- レジャーや用務のため、自分の投票区の区域外に旅行中か滞在中である場合
- 病気などで入院中か身体が不自由なため、歩行が困難な場合
- 天災または悪天候により投票所に到達することが困難な場合
期日前(不在者)投票できる期間・場所など
- 市役所
期間:選挙期日の公示(告示)日の翌日~投票日前日
時間:午前8時30分~午後8時
- 各公民館(17ヵ所)
期間:投票日の6日前(月曜日)~投票日前々日(金曜日)の5日間(祝日を除く。)
時間:午前8時30分~午後5時
- コムファースト・ショッピングセンター(アピタ足利店)
市長選挙・市議選挙
期間:投票日の6日前(月曜日)~投票日前日(土曜日)の6日間
時間:午前10時~午後7時
県議選挙
期間:投票日の8日前(土曜日)~投票日前日(土曜日)の8日間
時間:午前10時~午後7時
その他の選挙
期間:投票日の11日前(水曜日)~投票日前日(土曜日)の11日間
時間:午前10時~午後7時
郵便等による不在者投票
身体障がい者手帳または戦傷病者手帳を持っていて、身体に一定程度を超える重度の障がい(両下肢または体幹等の障がい)があり、歩行が困難で投票所に行けない選挙人で自書できる人は、在宅のまま投票できる郵便等による不在者投票の制度があります。
選挙運動
選挙運動とは、候補者の当選を目的として、投票を得たり得させたりするために、直接または間接を問わず、選挙人に働きかける一切の行為のことです。
選挙運動の期間
選挙運動は立候補の届出から投票日の前日までに限られ、この期間以外は、選挙運動をすることはできません。
選挙運動のできない人
選挙運動は、だれでも自由に行うことができるものですが、選挙の公正な執行を確保するため、次の表の人は、選挙運動を行うことが禁止されています。
| 区分 | 職業名など |
|---|---|
| 選挙事務関係者 |
投票管理者・開票管理者・選挙長及び選挙分会長 |
| 特定の公務員 |
中央選挙管理会の委員及びその庶務に従事する総務省職員・選挙管理委員会の委員及び職員・裁判官・検察官・会計検査官・公安委員会委員・警察官・収税官吏及び徴税吏員 |
| 年齢 |
満18歳未満の人 |
| 公民権停止中の者 |
選挙犯罪等を犯したため選挙権や被選挙権を有しない人 |
地位を利用して選挙運動のできない人
- 国または地方公共団体の公務員及び法律で定める公庫、公団の役職員等
- 学校教育法に規定する学校の長及び教員
- 不在者投票のできる施設に指定された病院、老人ホーム等の施設の長等
ポスターなどの制限
ポスター、立札、看板、ビラ、ハガキ等がありますが、それぞれ使用枚数や大きさに制限があります。
街頭演説の制限
街頭演説ができるのは、午前8時から午後8時までです。従事できる運動員の数は15人以内とされ、選挙管理委員会から交付された一定の腕章を着用するとともに街頭演説用の標旗を掲げなければなりません。
連呼行為の制限
短時間に一定の文句を繰り返ししゃべることを「連呼行為」といいます。
連呼は、選挙運動用自動車(船舶)の車(船)上か、街頭演説の場所及び個人演説会場の中でのみ許されます。
だれでもできる選挙運動
- 電話による投票の依頼
- バス・電車の中で出会った知人や友人への投票の依頼
- 個人演説会での応援演説
禁止されている代表的な選挙運動
戸別訪問の禁止
選挙運動の目的で戸別に選挙人の家などを訪問することは、すべての人に禁止されています。
飲食物の提供の禁止
選挙運動に関して、飲食物(湯茶、通常用いられる程度の茶菓子を除く)を提供することは、すべての人に禁止されています。
有権者が陣中見舞いとして酒などを持っていくことも禁止されています。
贈らない! 求めない! 受けとらない!
公職選挙法では、お金のかからないきれいな選挙を実現するため、政治家や候補者が選挙区内で寄附行為をすることを原則として禁止しています。
- 病気見舞い
- お祭りへの寄附や差し入れ
- 地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
- 葬式の花輪、供花など
- 入学祝、卒業祝、お中元、お歳暮
なお、有権者が政治家や候補者などに、このような寄附を勧誘したり、要求することも違反になります。
選挙管理委員会とは
市の選挙管理委員会は、市の議会の議員及び長の選挙に関する事務を管理し、法令によってその権限とされるその他の選挙に関する事務(国、県の選挙に関する事務)及びこれに関係ある事務を管理します。
- 委員の数、任期
選挙管理委員会は、4人の委員によって構成され、任期は4年です。 - 委員となる人
選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し、公正な識見を有す者の中から議会により選挙で選ばれます。 - 主な仕事
- 各種選挙の管理執行
- 選挙人名簿の調製、投票、開票、選挙公営の事務
- 住民投票の管理執行
- 直接請求に関する署名の効力の審査
- 啓発活動の実施
選挙人名簿とは
明るい選挙
選挙は、民主主義の基盤であるといわれておりますので、この選挙が金の力や不正な手段でゆがめられることがないように、市民の政治意識を高めていこうとするのが明るい選挙の推進です。
足利市選挙管理委員会では、『足利市明るい選挙推進指導員』の皆さんとともに明るい選挙の啓発に努めています。