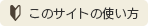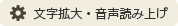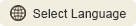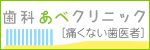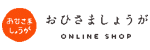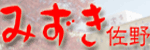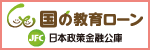【Q&A】「足利市立小・中学校の新たな学校づくり基本計画(原案)
足利市立小・中学校の新たな学校づくり基本計画(原案)に関する地域説明会での主なご質問と教育委員会の考え方
はじめに
- 足利市教育委員会では、「足利市立小・中学校の新たな学校づくり基本計画(原案)(新しいウィンドウが開きます)」について市民の皆様にご説明し、ご意見をいただく機会として、8月30日(土曜日)まで地域説明会等を開催しています。
- このページは、皆様の計画へのご理解を深めていただく一助となるよう、これまでの説明会でお寄せいただいた主なご質問と、それに対する教育委員会の考え方をQ&A形式でまとめたものです。
- 本計画はまだ「原案」の段階ですが、地域説明会(新しいウィンドウが開きます)、パブリックコメント(新しいウィンドウが開きます)のご意見を踏まえ、基本計画(成案)を取りまとめ、今年中を目途に教育委員会において決定し、市議会へ報告したいと考えております。
Q&Aの作成にあたって
- これまでの説明会での質疑応答の要旨であり、すべての発言を掲載するものではありません。
- 質問(Q)は、複数の説明会でいただいた同様の趣旨のご質問を一つに集約し、多くの方が疑問に思われる点を代表的な形で掲載しています。
- 回答(A)は、説明会でのご説明に加え、教育委員会の考え方をより分かりやすい内容となるように記載しています。
主な質問と教育委員会の考え方
質問一覧
- リンクから各質問と教育委員会の考え方に移動することができます。
(1) 計画の全体像・スケジュールについて
Q1.なぜ学校再編が必要なのですか。児童生徒数が少ないことの課題は何ですか。
Q2.小規模校には、先生と子どもの距離が近く、地域とのつながりが強いといった良い点もたくさんあります。計画では課題ばかりが強調されていませんか。
Q3.学校再編のスケジュールはどうなっていますか。第1期(南ブロック・北ブロック)は令和12年度から統合が始まるのですか。
(2) 教育内容・方法について
Q5. 「足利MIRAI教育」や「小中一貫教育」は、学校再編をしないとできないのですか。
Q6.足利市が取り組む「小中一貫教育」は、他市で行われているような小学1年生から中学3年生までが同じ校舎で学ぶ「義務教育学校」になるのですか。
Q7. 「チーム担任制」や「教科担任制」が導入されると、担任の先生と子どもとのかかわりが減るのではないかと心配です。
(3) 児童・生徒への支援や学校生活について
Q8.学校が新しくなると、環境の変化に馴染めない子どもが出てくるのではないかと心配です。
(4) 通学の安全対策や方法について
Q9.学校再編によって通学距離が長くなりますが、安全対策はどうなりますか。特に低学年の子どもの通学が心配です。
(5) 学童保育について
Q11.学校再編によって学校が遠くなった場合、放課後児童クラブはどうなりますか。
(6) 地域との連携や跡地活用について
Q12.学校が統合されると、地域のコミュニティが衰退してしまうのではないかと心配です。
Q13. 閉校した学校の建物や土地(跡地)はどうなりますか。
(7) 計画の進め方・意見の反映について
Q14.説明会で意見を言っても、計画はもう決まっているのではないですか?本当に市民の意見は反映されるのですか。
(1) 計画の全体像・スケジュールについて
Q1.なぜ学校再編が必要なのですか。児童生徒数が少ないことの課題は何ですか。
- 複式学級や学年単学級(クラス替えができない学級)が増加しており、子どもたちが多様な考えに触れる機会や、集団での学び合いといった活動に制約が生じるなどの課題があります。
- この基本計画では、子どもたち一人ひとりの教育環境をよりよいものにすることを最優先に考えています。クラス替えができる学校規模を確保することで、いろいろな考え方をもつ仲間と出会い、多くの仲間と話し合い、協力し合うグループ学習が充実したり、少人数学習や習熟度別学習、複数の教師によるチームティーチングも可能となるなど、これまで以上に、多様な学びの機会を提供し、子どもたちが主体的に学び、深い学びへとつながる環境を整備していきます。
- この計画は、これからの時代をたくましく生きる子どもたちの力を育むことを目指しています。
Q2.小規模校には、先生と子どもの距離が近く、地域とのつながりが強いといった良い点もたくさんあります。計画では課題ばかりが強調されていませんか。
- この基本計画原案では、児童生徒数が減少し、学校規模が小規模化すると、子どもたちが新しい友人関係を築く機会が減ったり、コミュニケーション能力、協調性や社会性を高める機会が得られにくくなるほか、教育活動の幅が狭まったり、教職員配置の偏りが生じるなどの課題を挙げています。
- ご質問の、小規模校ならではの、きめ細やかな指導や温かい雰囲気といったよい点は、十分に認識しています。足利市学校教育環境審議会の答申にも、「一人ひとりに目が届きやすく、きめ細やかな指導が行いやすい」「子どもたちがリーダー等を経験する機会が多い」「地域との連携がしやすい」といった、小規模校ならではのよさも挙げています。
- この計画は、そのよさを否定するものではありませんが、学校再編によって一定程度の学校規模を確保することで、小規模校のよさを生かしつつ、例えば、体育でのチーム対抗の試合や、音楽での合唱・合奏など、ある程度の人数が集まることで、子どもたちの深い学びや心の成長へとつながる環境を整備し、教育の質のさらなる向上を目指したいと考えています。
Q3.学校再編のスケジュールはどうなっていますか。第1期(南ブロック・北ブロック)は令和12年度から統合が始まるのですか。
- この計画では、令和8年度から4年間を準備・協議期間とし、通学方法や新しい学校名などを地域や保護者の皆様と話し合います。そして、準備が整った5年目となる令和12年度から新しい統合校への通学を開始することを標準的なスケジュールとして想定しています。
- 第2期以降のブロックについても、例えば、第2期においては第1期中、第3期においては第2期中において、改めて児童生徒数の推計を行い、統合校の位置などの具体的な計画案をお示ししながら進めていきます。
Q4.統合校の場所はいつ頃決まりますか。
- 第1期で学校再編に取り組むブロックについては、計画(原案)の中でお示ししています。 第2期以降のブロックについては、児童生徒数の推移などを把握する必要があるため、例えば、令和12年度から始まる第2期においては、その1~2年前の令和10年度から令和11年度を目途に、統合校の位置などについて具体的な考え方をお示ししたいと考えています。
(2) 教育内容・方法について
Q5.「足利MIRAI教育」や「小中一貫教育」は、学校再編をしないとできないのですか。
- 「足利MIRAI教育」や「小中一貫教育」の取組は、再編を待たずに取り組んでいます。再編により一定程度の学校規模を確保することで、教職員の配置が充実し、教科担任制やチーム担任制といった取組をより効果的に進めることができます。
- これにより、児童生徒にとっては、専門の先生からより分かりやすく質の高い授業を受けられたり、たくさんの友達と多様な意見を交わしながら協力して学んだりする機会が増え、教育の質をさらに高めることができると考えています。
Q6.足利市が取り組む「小中一貫教育」は、他市で行われているような小学1年生から中学3年生までが同じ校舎で学ぶ「義務教育学校」になるのですか。
- 足利市が取り組む「小中一貫教育」は、既存の学校施設を活用し、これまでどおり、小学校と中学校が別々であり、修業年限も、小学校は6年、中学校は3年の「6-3制」を維持します。
- 小学校の卒業や中学校への入学といった「節目」や「段差」を経験することにより、目標に向かって困難を乗り越える力や気持ちを新たにして中学校生活をスタートできることを大切にしています。具体的には、お子さんが小学校の最上級生としてリーダーシップを発揮したり、中学校入学で気持ちを新たにして目標をもつといった、それぞれの学年での大切な経験や成長を重視しています。
- 足利市では、この「小中一貫教育」を推進し、小学校から中学校の9年間のつながりを大切にした教育内容(カリキュラム)や、小・中学校の先生の連携を図り、児童生徒一人ひとりの学びや成長を小学校と中学校が一体となってきめ細かく支えていきます。
Q7.「チーム担任制」や「教科担任制」が導入されると、担任の先生と子どもとのかかわりが減るのではないかと心配です。
- 「チーム担任制」は、小学校段階、特に低学年のお子さんにとって担任の先生との信頼関係を重視し、担任の補助的な役割を担う職員を配置する取組です。
- また、「教科担任制」は、発達の早期化による課題の解消や中1ギャップへの対応を図るため、主に小学校高学年に導入する取組です。これにより、専門的な知識を持つ先生から深く学ぶことができるメリットがあります。
- さらに、 「チーム担任制」と「教科担任制」を導入することにより、担任一人だけでなく、多くの先生が一人の子どもとかかわることにより、子どもたちの小さな変化にも気づきやすくなると同時に、より多角的な視点で一人ひとりに寄り添いながら、子どもたちの理解を深めることにつながると考えています。
(3) 児童・生徒への支援や学校生活について
Q8.学校が新しくなると、環境の変化に馴染めない子どもが出てくるのではないかと心配です。
- 新しい環境への不安を少しでも和らげるため、学校再編前から、一緒になる学校同士の児童生徒が交流する機会を計画的に設け、特に「足利MIRAI教育」では、同じブロック内の小・中学校の連携をより一層深めていきます。さらに、スクールカウンセラーや栃木県のスクールソーシャルワーカーなどとも連携しつつ、一人ひとりの心のケアにこれまで以上に丁寧に取り組んでいきます。
- また、今年度から全ての中学校に、安心して過ごせる居場所(スペシャルサポートルーム)を設置し、悩みを相談しやすい環境をつくりました。 学校再編後は、複数の教職員で学級を見る「チーム担任制」を一層推進し、一人ひとりの変化に気づきやすい体制を整えます。
- なお、不登校傾向にあるお子さんなどが安心して学べるよう、新たな学びの場の選択肢についても研究しております。全国の事例なども参考にしながら、足利市としてどのような支援の形が望ましいか、引き続き検討していきます。
(4) 通学の安全対策や方法について
Q9.学校再編によって通学距離が長くなりますが、安全対策はどうなりますか。特に低学年の子どもの通学が心配です。
- 児童生徒の通学の安全確保は最優先課題であると認識しています。
- 学校再編によって通学路が新しくなる地域では、国、県、警察、そして地域の皆様と緊密に連携し、通学路の安全点検や安全対策を徹底してまいります。地域や保護者の皆様からのご意見も伺いながら、危険箇所の情報収集や不審者対策なども含めて、きめ細やかに対応していきます。
Q10.スクールバスの運行はどのように考えていますか。
- 通学距離が長くなる地域においては、スクールバスが必要になると考えており、運行にかかる費用は、学校再編を進める上で不可欠な経費として責任をもって予算確保に努めます。
- 現在、対象地域での運行シミュレーションを行っており、今後設置する検討委員会の中で提案させていただき、具体的な運行ルートやバス停の位置、時間などについて、地域や保護者の皆様のご意見を伺いながら決定していきます。
(5) 学童保育について
Q11.学校再編によって学校が遠くなった場合、放課後児童クラブはどうなりますか。
- 共働き家庭が増える中、放課後児童クラブの重要性は認識しています。
- 学校再編に伴う放課後児童クラブのあり方については、現在の場所で継続する方法や、統合先の学校に集約する方法など、様々な選択肢が考えられます。市長部局の放課後児童クラブを担当する部署とも連携しながら、 スクールバスの活用も視野に入れ、保護者や地域の方々のニーズを丁寧に伺いながら、よりよい形を検討していきます。
(6) 地域との連携や跡地活用について
Q12.学校が統合されると、地域のコミュニティが衰退してしまうのではないかと心配です。
- 学校が地域コミュニティの核となってきたことは、十分に認識しています。
- 学校再編後も、これまで育まれてきた地域と学校のつながりが薄れることのないよう、学校運営協議会(コミュニティ・スクール)の仕組みを活用し、より広い範囲で地域が一体となって子どもたちを育てる関係づくりを目指します。そのためのつなぎ役となる地域コーディネーターの配置も進めていきます。
Q13.閉校した学校の建物や土地(跡地)はどうなりますか。
- 閉校後の学校施設は、市のまちづくり全体の視点から、公共施設としての利用や民間活用など、最も有効な活用方法を検討していきます。学校再編が決まった後、早い段階から皆様と一緒に考えていきたいと思っています。
(7) 計画の進め方・意見の反映について
Q14.説明会で意見を言っても、計画はもう決まっているのではないですか。本当に市民の意見は反映されるのですか。
- 今回、お示ししているものは、新たな学校づくり基本計画の「原案」です。これは、令和3年度に学識経験者や保護者、地域の皆様にも参画いただいた「足利市学校教育環境審議会」での約2年間にわたる議論を経て、その答申を基に作成したものです。
- 現在実施している説明会やパブリックコメントは、皆様からご意見をいただき、計画をよりよいものにしていくために実施しています。 いただいたご意見については、内容を検討し、反映できるものは反映させ、成案としてまとめます。
- パブリックコメントの結果についても、市の考え方とあわせて市ホームページで公表する予定です。
ご意見をお寄せください
- 「足利市立小・中学校の新たな学校づくり基本計画(原案)」に関するパブリックコメント(市民意見公募)を【令和7年9月5日】まで実施しています。
- 詳しくは、ホームページ(新しいウィンドウが開きます)をご覧いただくか、教育総務課新たな学校づくり推進室(直通0284-20-2365)までお問合せください。
掲載日 令和7年8月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
教育委員会事務局 教育総務課 新たな学校づくり推進室
住所:
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地
電話:
0284-20-2365
FAX:
0284-20-2215